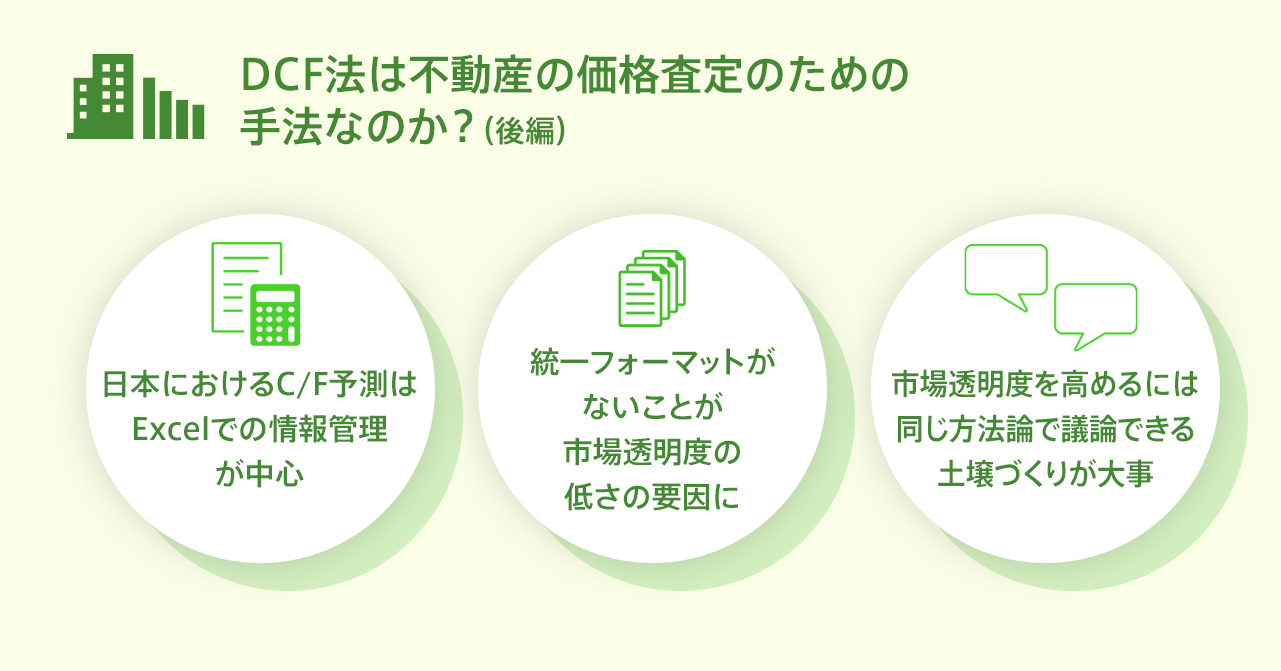不十分なキャッシュフロー予測と市場透明度の低さ
前回ご紹介したとおり、日本ではDCF法は不動産の価格査定手法としてのみ認識されているため、キャッシュフローの予測は欧米ほど重要視されていません。日本にもARGUSが上陸しましたが、大学の研究者を含め、欧米で一般的に行われている「リースバイリース分析」によるキャッシュフロー予測手法の存在を知っている業界関係者が、日本にはほとんど存在していなかったことや、関係者間の情報共有が重要視されていなかったことから広まりませんでした(※4)。
※4:ARGUSはすでに日本から撤退。
日本で作成されているキャッシュフローは、現時点のキャッシュフローを初年度として、2年度以降は空室率と賃料などを年度ごとに変動させて作成しているものが多いようです。信じ難いことに、なかには全期間にわたり初年度から変化のないキャッシュフローが用いられることもあります(※5)。価格を算出するという目的のためだけに、キャッシュフロー予測に時間をかけられないためです。
※5:このようなキャッシュフローの場合、割引率と最終還元利回りが同じ値であれば直接還元法を行っているのと変わらないことになります。
その結果として、日本のキャッシュフローには、前回ご紹介した9つの不動産事業リスクのうち、ビジネスリスクが若干含まれている程度となっています。このようなキャッシュフローを作成するだけならば、複雑な計算が不要であるためExcelで十分です。
実際、現在でも日本ではExcelが主に利用されています。2007年の不動産鑑定基準改正で収支項目が規定されていますし、昨今では会社ごとのフォーマットが統一されつつある一方、投資家、不動産鑑定士、金融関係者、不動産業者などが同じフォーマットを使用するには至っていません。これが日本の不動産市場の透明度の低さの要因の1つとなっています。
DCF法には、賃料や空室率の動向調査と将来予測、収益還元利回りや、最終還元利回りなどの情報調査、キャッシュフローの作成など、直接還元法よりも多くの情報収集が必要となります。日本では、市場の情報入手が未だに困難です。それゆえに不動産証券化以外の取引ではDCF法はほとんど利用されず、直接還元法が主に利用されています。
分析手法の統一とそれを支えるシステムの重要性
また、日本では、金融工学的な考え方で確率分布を用いてキャッシュフローを生成し分析するDDCF(Dynamic Discounted Cash Flow)法がもてはやされた時期がありました。一方で、欧米においては一貫してDCF法が用いられています。不動産については、地道に情報を積み重ねることで、確率分布を用いるよりも現実的でリスクマネジメントの観点からも優れているキャッシュフローを予測することができるからです。
今後の研究によって、精度が高く、リスクマネジメントの観点からも優れたキャッシュフローを生成できるDDCF法が開発される可能性は否定しませんが、現状においてはDCF法の方が実用に適しています。
金融工学は金融商品の過去のデータを分析し、リスクの最小化、リターンの最大化などを研究する学問であり、コンピューターの進化とともに発展してきました。しかしながら、過去の動向だけでは予見できない事象は多く発生します。潤沢なデータが存在する株式などの市場動向についても、半年後の予測すらできないのです。エコノミストやシンクタンクが発表している経済予測も同様です。
これらは、将来予測が非常に困難であるという事実を如実に表しています。このため、投資においては、定期的に将来予測(フォーキャスト)を見直し、都度リスクを洗い出し、対応策を再検討するという地道な作業が必要です。
投資用不動産の将来のキャッシュフロー予測に対する変動要因については、売り手、買い手、投資家、金融機関、不動産鑑定士それぞれの立場によって変わります。たとえば、売り手は物件価値がより高くなるように条件を緩くしますし、買い手や金融機関は厳しく査定するでしょう。
関係者間で同じシステムを利用し、現状の不動産情報(テナントの契約条件や現在のキャッシュフローなどを含む)については仲介業者などが入力したデータを使用し、変動要因の査定部分を明らかにすることができれば透明度は大きく向上しますし、各々の関係者がデータを入力する手間が省けるので取引に要する期間も短縮できます。
また、こうした物件情報を買い手が活用することで、物件管理やリスクマネジメント、キャッシュフロー分析における生産性も大きく向上します。夢物語のような話ですが、欧米では20年以上前に実現しています。
これは、データが公開されていることに加え、同じ手法でDCF法を活用していること、それを支えるシステムがあることが前提です。英語を使う国であったからできたことではありますが、オーストラリアは国策で複数の大学に不動産学部を設立し、欧米と同じ教科書を使って人材育成を行いました。
日本においても、欧米のように不動産ファイナンスに関して大学などの教育機関で基礎知識や応用知識を教育する体制を整え、市場関係者が同じ方法論のもとで議論ができる土壌をつくる必要があるのではないでしょうか。

藤井和之(ふじいかずゆき) 不動産市場アナリスト
1987年 東京電機大学大学院 理工学研究科 修士課程修了、清水建設入社
2005年 Realm Business Solutions(現ARGUSSoftware)
2007年 日本レップ(現GoodmanJapan)
2009年 タス
2022年~現職
不動産流通推進センターの機関誌「不動産フォーラム21」ほか執筆・セミナー活動を実施
著書 大空室時代~生き残るための賃貸住宅マーケット分析 住宅新報出版
不動産証券化協会認定マスター、宅地建物取引士
MRICS(英国王立チャータード・サーベイヤーズ協会)メンバー
日本不動産学会、日本不動産金融工学学会、資産評価政策学会会員